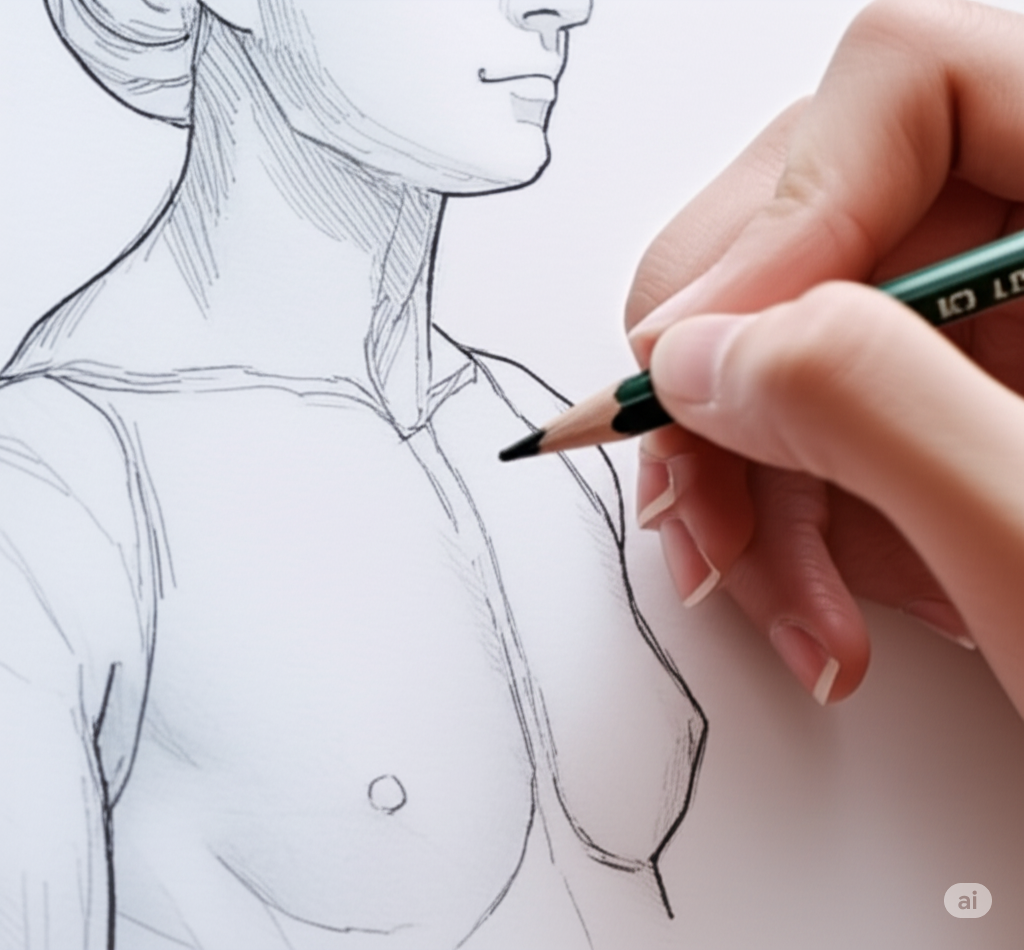
公開前から主演に関するネガティブな報道が先行し、初動への影響が懸念された映画『かくかくしかじか』。しかし、実際に劇場で観た後、その懸念は杞憂だったと確信しました。作品そのものが持つ力、そして俳優陣の熱演が、あらゆる逆風を跳ね除け、多くの観客の心を深く捉え、高い評価を得ています。私自身も、この「世間的な高評価」に強く同意する本作の真価に迫ります。
「世間の高評価」に同意する理由
私が本作の評価に同意する理由は、主に以下の点に集約されます。
- 感動的で普遍的な物語: 多くの映画レビューサイトで平均点が4点前後(5点満点)を推移しており、「泣けた」「勇気をもらった」といった声が多数を占めます。これは、単なる面白い話に留まらず、人生の節目や困難に立ち向かう普遍的なテーマが多くの観客に響いた証拠です。
- 俳優陣の卓越した演技: 特に大泉洋さんと永野芽郁さんに対する演技の称賛は、レビューの多くで共通しています。彼らがキャラクターに息を吹き込み、物語に説得力と深みを与えたと評されています。
- 演出と映像美: 単調になりがちな自伝的物語を、巧みなロケーション選択やテンポの良い編集で魅せる演出が評価されています。
これらの要素が複合的に作用し、批評家だけでなく一般の観客からも高く支持されているのが本作の現状であり、私自身の評価もその流れに強く同意するものです。
リアルを極めたシナリオと心揺さぶる絵作り
本作最大の魅力は、漫画家・東村アキコ先生の自伝的エッセイを原作としている点にあります。描かれるエピソードのほとんどが事実に基づいているため、物語には圧倒的な説得力と、観客が自身の人生と重ね合わせたくなるような普遍性が宿っています。
特に印象的だったのが、「絵作り」の巧みさです。宮崎、金沢、東京と舞台が移り変わることで、画面に心地よい変化が生まれ、観客を飽きさせません。「邦画にありがちな閉塞感」とは、一般的に、限られたセットや少数の登場人物、室内でのシーンが多く、画角が狭く感じられ、物語の世界が窮屈に映ることがある点を指します。しかし、本作では宮崎の広々とした風景が冒頭に登場することで、その狭苦しさを全く感じさせず、主人公の若き日の伸びやかさや、まだ何者でもない解放感を視覚的に表現していました。それぞれの土地が持つ空気感や色彩が、物語の段階や主人公の感情の機微と見事に同期し、映像としての奥行きを深めています。
俳優陣の魂のこもった熱演と、その化学反応
この映画の成功は、ひとえに俳優陣の熱演と、彼らが織りなす化学反応に支えられています。
日高先生を演じた大泉洋さんは、これまでの彼のパブリックイメージとは異なる、時に厳しく、時に優しさを見せる複雑なキャラクターを、見事に血肉化していました。彼の独特な発声や間の取り方が、日高先生の不器用ながらも生徒を思う情熱をリアルに伝え、観客に「彼が日高先生そのものだ」と強く感じさせる説得力がありました。これは、単に役柄を演じるという以上に、彼自身の個性が日高先生のキャラクターと奇跡的な融合を果たした結果だと感じます。
そして、主人公を演じた永野芽郁さんもまた、その瑞々しい演技で物語を牽引します。高校生時代の奔放さ、美大で情熱を見失いかける焦燥、そして漫画家として葛藤する大人の女性へと変化していく姿を、飾らない自然体な表現で演じきり、観客が主人公の成長に深く共感できるよう導いていました。彼女の泣きの演技だけでなく、日常の中でのふとした笑顔や困惑した表情が、キャラクターの人間味をより深く引き出していました。
さらに、脇を固める俳優陣も物語に温かい彩りを添えました。特に主人公の両親役は、家庭の温かさや親が子を見守るまなざしを、過剰な演出なく自然に表現しており、物語のリアリティを支える重要な存在でした。MEGUMIさん演じる母親は、おおらかでどこか楽天的ながらも、娘を見守る愛情がにじみ出ており、大森南朋さん演じる父親は、多くを語らずとも娘への深い理解と優しさが伝わる、まさに理想の父親像でした。彼らの何気ない会話や、時にユーモラスなやり取りは、物語に良い緩急を生み出し、観客の心を和ませる効果をもたらしています。
「なんとなく」に宿る真実のリアリティと監督の視点
美術大学での主人公の描写は、多くの観客にとって驚きであり、同時に強い共感を呼ぶでしょう。絵に没頭するどころか、恋愛に明け暮れ、絵への情熱が冷めかけていく姿。そして、その恋愛関係もまた「なんとなく自然消滅」という、あっけない幕引きを迎えます。
一般的なドラマでは描かれがちな、劇的な出会いや別れとは一線を画すこの「なんとなく」の描写こそが、人生のリアルを映し出しています。常に何かが劇的に終わるわけではない。だからこそ、そうした日常の曖昧さの中に、日高先生との出会いと、そこから得た「絵を描き続ける」という情熱が、どれほど主人公の人生においてかけがえのないものだったかが、より一層際立つ構造になっています。
受験期に実践されたという「ダウジング」のエピソードも、まさかの実話。これには思わず「嘘のような本当の話だ!」と笑ってしまいました。これは、東村先生の人間味あふれる一面と、日高先生の常識にとらわれない教育方針を示す、ユニークなエピソードとして強く印象に残っています。
本作の演出を手掛けた関和亮監督は、派手なギミックに頼ることなく、実話が持つ生々しいまでの感情を誠実にすくい上げようとしたように見受けられます。過度な説明を排し、役者の表情や「間」で多くを語らせる手法は、観客の想像力を掻き立て、作品への没入感を高めます。特に終盤、日高先生の存在感が主人公の創作活動に強く影響を与える場面では、VFXを用いた表現が、漫画的な面白さと映画ならではの視覚的なダイナミズムを両立させており、観客の心を強く揺さぶりました。
邦画において、時に過剰に感じられる「長すぎるクローズアップ」は、観客に感情を押し付けたり、単調さを生んだりすることがあり、個人的にはあまり好みではありません。しかし、『かくかくしかじか』では、確かにアップは多用されているものの、その秒数が短く抑えられている点が非常に巧みでした。これにより、役者の繊細な表情や内面を効果的に表現しつつも、物語の流れや映像全体のテンポを損なうことなく、観客が心地よく作品に没入できるよう配慮されています。このバランス感覚こそが、本作の演出の質の高さを物語っていると言えるでしょう。
総評:逆境を乗り越え、真価を証明した傑作
公開前のネガティブな話題があったにもかかわらず、映画『かくかくしかじか』は、その作品自体の力と俳優陣の熱演で、多くの観客の心に深く刻み込まれる傑作となりました。恩師との出会いと別れ、そして夢に向かって「描くこと(続けること)」の大切さを描いたこの作品は、クリエイターだけでなく、人生の岐路に立つすべての人々に響く普遍的なメッセージを持っています。
この映画が、公開前の話題性を超えて、最終的に作品の質で正当に評価されたことは、日本の映画界にとっても、作品の本質が正しく評価されることの重要性を示す大きな意味を持つでしょう。私にとって、この作品は心に深く残る一本となりました。